中山善之先生『老人と海』刊行記念インタビュー
2013年9月発売の『老人と海』の訳者、中山先生に
本書を訳されたときのお話をお伺いしました。
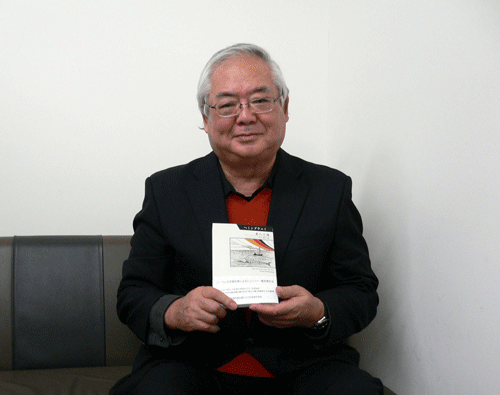
(訳書『老人と海』を手にする中山善之先生)
〈『老人と海』の新訳にあたって〉
編集部 今回『老人と海』を新訳されるにあたって、どんなところに気をつけて訳されましたか?
中山善之先生(以下「中山」) 一番気をつけたのは、老人と少年の関係をどう表現するかですね。気持ちは通い合っているんだけど、その接点がどこにあるのか。おじいさんは、一介の無学な漁師かもしれないけど、その長い生活を通じていろいろ感じてきているわけですよね。その感じ方がとても純粋なんでしょうね。少年はその老人の中に一途な精神、綺麗な精神を感じて、感動して、呼応していく。そういった感じを出したいと思ってやりましたね。
あとがきにも書いたんですけど、実際の老人は55、6歳だろうと思うんです。時代がだいぶ違いますからね。それで僕なんかもう70を過ぎているんだから、おじいさんの気持ちをどこまで訳せるか、そこが一番気になったところですね。それと、少年の老人に対する一途な敬愛の情、ちょっと言葉は荒っぽくてもやさしく接している感じを出そうと思いました。訳に関して言えばそういうことですね。
編集部 本書のあとがきでも書かれていますが、今までの翻訳者は、この“老人”よりも若い時に訳されていますから、そこが今までの訳者と大きく違うところなんですね?
中山 そうですね。だいぶ感覚が違うんだと思うんですよね。僕はこの老人に愛情を感じるんですよね。それがうまくいったかどうかはわからないけど……。
編集部 一番苦労したところはどこですか?
中山 一番苦労したところは、簡単に言えば、少年がじいさんを呼ぶときに何と呼ぶのがいいか。「じいさん」がいいのか「おじいさん」がいいのか「ジジイ」がいいのか。老人が自分を励ますところでも、「じいさん」とか「じじい」とか、多少変えてみたんです。その時の主人公の気分によってね。
ごく普通の言葉から、老人と少年の気持ちが通い合っている、お互いに許しあっている、二人だけは素直にちゃんと分かり合えているというのが伝わるようにね。そういう言葉を探すのが難しいんですよね。
編集部 一言で雰囲気を表現されているんですね。
中山 そうね、ぱっとお互いに気持ちがわかり合えるというか、他人が聞いたら荒っぽいような言葉だけど愛情がこもっている、そういう言葉を一生懸命探しましたね。
あと、技術的なことだけど、釣の道具や糸なんかに関しても苦労しましたね。今ならナイロンの一本の糸だけど、この時代は撚り糸で紐みたいなものだからね。今ならラインでいいんでしょうけど、ラインだと現代的過ぎるからね。撚り糸だから釣綱とか変な言葉になっているけど、古い日本語だとああしか言いようがないみたいで、まあ妥協しちゃったんですけどね。そういう点が難しかったですね。
編集部 当時の漁に関してもいろいろと調べられたんですか?
中山 まあ、ぼくは魚釣りを何十年もやっているからね。下手くそだけど。だから気持ちはよくわかるんですよ。魚がかかった瞬間の気持ちとか、魚の反応とかね。この小説とはスケールは違いますけどね。でも、はっとした瞬間の動きとかね、それは多少わかるんですけど。ラインが困ったんですよね。釣り仲間に聞いてみたりしてね。今とは道具の言葉が違いますから。昔は紐で撚ったものを使って、それで手が焼けたりしてね。そのへんが難しかったけど、時代的な感覚のずれは出てきても、それは仕方がないと思いますね。原文の時代をある程度尊重しないといけないですしね。
それから、僕が多少助かったのは、TIME-LIFE社の編集者時代にね、海とか魚とかに関する本を何種類も編集を担当しているんです。東大の「お魚博士」と言われた末広恭雄さんとかに監修してもらった本もありました。その後、一緒に酒を飲みに行くようになったりしましてね。まあ、そういう本をやっているので非常に役に立ちましたね。そういう本も持っていますから、当時の。それを見ながらね。
それからこれは余談ですけどね、この本の中にカツオノエボシというくらげが出てくるんですよね。このくらげがね、誰かの訳ではまったく間違っているというか、わからなかったんだろうね。難しくいえば浮嚢(ふのう)、一般的には傘というんだけど、そういったところがね。まあ、そういう魚の勉強が少し足りないような感じがしましたね。まあ、仕方ないんだけども、昔の話ですからね。久しぶりの新訳で、そのへんは少しは直せたかなと思っています。
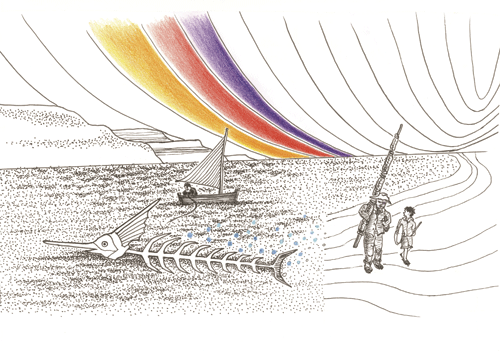
(『老人と海』(柏艪舎版):カバー画)
〈『老人と海』の名シーン〉
編集部 本書の中で一番気に入っているシーンはどこですか?
中山 そうねえ、帰ってきたじいさんがくたびれて寝ているところだね。いろんな取り方があるだろうけど、あれを人生だと思ってもいいだろうし、むなしいと感じる人もいるかもしれないけどね。ただ、今回の訳は先輩たちの訳とは違っています。登場人物は男ばかりだから男と訳してありますけど、「男たるもの打ちのめされてはならない。自滅することはありえるが、打ちのめされるのは許されない」と。そういう風に僕は訳したんですけどね。じいさんはむなしいんだ、という結論を出す人もいるかもしれないけど、あのじいさんの場合はあれで満足していると思いますね。打ちのめされなかった、徹底的に闘ったと。それで魚に対しても敬意を持って、きみもよく闘ったなあ、僕もよく闘った、これで満足だ、またチャンスがあったら挑戦するぞ、くらいの気持ちで眠っているんだと思うんですよ。僕はこの本をそういう風に読んでいるので、寝ているところが可哀想なようだけど一番良いところなんじゃないかって感じているんです。
それと、もう一つの良い場面は、「星や太陽を殺さない」と考えているでしょ、毎日俺たちが星や太陽を殺す羽目になったら嫌だなと。鳥に対しても、飛んできた鳥に対してすごくやさしいでしょ。ああいうシーンがとても良いですよね。僕は人間としての一番大切なことはやさしさだと思うんです。あのじいさんは無学かもしれないけれど、それがちゃんと滲み出てきている。そういう目で見ると、この作品はなかなかのもんだなと思いますよね。人間は精神的に打ちのめされたと思ったらだめだ、だから人間は不屈でいられる、ということですよね。そういう風に僕は訳したんです。そのへんが、今までの訳者の方とはちょっと違うところだと思います。
編集部 男たるもの打ちのめされてはいけないと。
中山 そう、自滅しちゃいけない。「自滅することはありえるが、打ちのめされるのは許されない」ということ。自滅されたらおしまいだよ、論外だから。だから、このじいさんはこうやって生きてきたんでしょうね。
〈ヘミングウェイについて〉
中山 ここにすごさがあってね。これは僕の偏見と独断だけど、ヘミングウェイは自殺しているでしょ。ヘミングウェイは、僕に言わせると、日本でいえばニヒリストですよ。作家になるためにいろいろと経験しようとしたんでしょうけど、スペイン戦争に参加したりしてね。結局、小説を書いても、『日はまた昇る』でもそうですけど、しっかりした男も女も書かれていない。世の中を拗ねてるとか、捻くれているというか、流れて生きているというか、そういう人ばかり。スペイン戦争に行ったゲリラの人たちは一途に打ち込んでいるんだけど、一瞬にして虚しく死んでいるわけですよね。
僕が思うに、ヘミングウェイは何をやっても虚しさを感じていたんじゃないかな。だからね、次々といろんなことをやるんですよ。飛行機で空を飛んだり、魚釣りをしたりね。でも、どうしても生きていることに虚しさを感じていたんじゃないかって僕は思っているんですよね。
『老人と海』でも必死なんですよね。生きがいを感じるというか、徹底的に自分のありったけの力を打ち込んでみたいと必死になっているわけですよ、ある意味では。だけど、結局、そういう風にはいかなかった。魚をとって、きれいに浜まで持ってきて、売って、成金にはなっていないわけですよ。これがヘミングウェイの一生を象徴しているのかもしれないと感じますね。

(1950年ごろのヘミングウェイ)
〈ヘミングウェイの英語〉
中山 英語で読むと、ヘミングウェイは簡単な言葉で書いてあります。だからかえって難しい。どれだけの意味を持って言っているのかなかなかつかめない。僕が教えている教室で、英語で小説を読みましょうということをやっています。シャーウッド・アンダーソンという、ヘミングウェイに影響を与えたという作家を読んでいるんですけど、これも簡単な英語で書いてあるんですよね。だけど、なかなか意味がわからないと生徒は言うんですよね。どうしてかというと、僕たちが生まれて初めて英語を習ったときに、覚えた単語の意味はたいてい辞書に載っている第一の意味なんですよね。でも五十番目くらいまで意味があって、ヘミングウェイやシャーウッド・アンダーソンはその五十番目の意味で単語を使ってくる。だから、ぜんぜん話が合わないんですよ。
編集部 指示語も多いですよね。
中山 どう考えても間違いじゃないか、と思うところもあるんだけど、そうじゃないんですよね。文法的に考えてもね、老人は「海なら絶対迷わない」っていうんですよ。老人は長年海で暮らしているんだから、星もあるし、行けると。その後の部分が、「それに、キューバは長い島だ」という訳になるんですよね。僕には、それがどうしてもキューバとは思えないんだけどね。地図を見ると確かにキューバは結構長い。長いけど、海は広いんだし、いくらキューバが長くたって……。世界で六番目くらいに長い島らしいんですけどね。だから僕は、「海は広くて、いくら長くてもどこかに行く一本道みたいなものだ」と訳してたんだけどね。でも、先輩の訳はみんな「キューバは長い」と書いてあるんですよ。ネイティブに確認してもみんなそうだっていうんですよね。だから、海をたどっていけばキューバに戻れるよ、という意味だと解釈したんだけどね。“it is a long island”って書いてあって、“it”は前の文章を受けると“海”だと思ったんですよね。いきなりでてくるんですよ、“it”がね。
編集部 キューバとは書いていないんですか?
中山 書いてないんですよ。海は広くてなんだかんだといって、いきなり“and it is a long island”と続くんですよ。だから、いくら長いといっても航海して行けばそこに戻るという意味だろうと、そっちのほうがかっこいいんじゃないかなと思ったりして。まあ、そんなふうに妥協したところもあります。
〈ヘミングウェイと日本の作家〉
編集部 『老人と海』は今まで何度もお読みになっていると思いますが、今回新たな発見はありましたか?
中山 若いときは、ただザーッと読んで、「ああ、読んだ」という感じだったけど、今はもう遥かに後期高齢者になっていますからね。これはたった四、五日の魚釣りのようですけどね。それが一生だととれるんです。理屈じゃなくてね。人生は長くていろんなことがあって、ということが考えられますからね。年をとるのもまんざら捨てたもんじゃないと思うんですよね。高校時代にも読まされて、大学時代にも読んだし。中年の四、五十でも読んだかもしれないけど、ヘミングウェイの『老人と海』はそんなにいいもんかいな、くらいに思っていたけど、今回訳してみるとかなり重いものを感じましたね。
ヘミングウェイも、さっきの話に戻りますけど、えらく寂しい人だったのかなと思ったりね。それに五回も離婚しているっていうから、我が強くて個性が強すぎたのか、はたまたデーモンがついていたのか。それが作家として成功させたのかどうかわからないけど。まあ、業の深い男なんだろうな。そしてスケールの大きな人だったんでしょうね。そういった印象を持ちますね。
それに比べて、日本の作家、石川淳や森鴎外、森鴎外なんかは陸軍軍医の総監までつとめて最後は「森林太郎として死にたい」と遺書を残して肩書きはいっさい書かないでくれと言って死んでいった。立派だとは思うけど、太宰治とかその後の坂口安吾というのは文句ばかりたれて実際に行動はしなかった。西洋人と東洋人の違いかもしれないけど、ヘミングウェイは大変な行動力で自分の業というか、何かを一生懸命探し求めた人だと思います。日本の作家、特に太宰治や坂口安吾なんかと比べると、スケールの違いを感じますよね。
もっとも、ヘミングウェイの友達のフィッツジェラルドになると、日本のそういう人たちと同じような生活をして、破滅型になって、それで死んじゃっているわけですけどね。
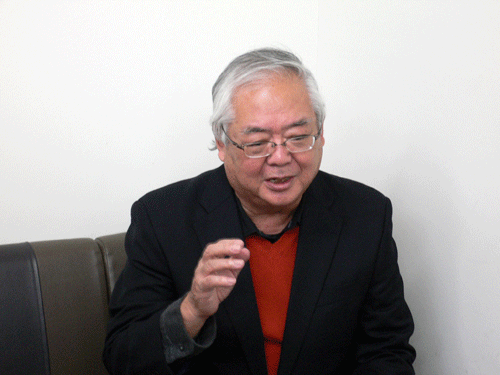
〈中山流翻訳論〉
編集部 翻訳論についてお聞きしたいんですけど、中山先生が普段翻訳をされるうえで注意されている点などありましたら教えていただけますか。
中山 最近特に思いますけどね。昔はね、こういう風に考えていたんです。翻訳の名訳ってあるでしょ。それには反対だったんです。英語をちゃんと訳したら、必ず読みづらいはずなんです。英語には必ず主語があるし、代名詞があるし。それがアメリカの文化、個人主義というか、それがある程度残らないとだめだと思うんですよね。少しバタ臭いなというのが残るのが本当なんじゃないかと思っているんです。極端な言い方をすると、さらっと意味をとって訳してしまうと、誰が書いても同じ文章になってしまうわけですよね。
原作では作家がわざわざこういう単語を選んで、組み合わせているんだから、それを日本語に書き直したら少し生な感じがするかもしれないし、幼い感じがするかもしれないし、えらくバタ臭い感じがしたりするかも知れないけど、それを活かしてなおかつ読めるようにするのが良い翻訳だと思うんです。でも必ずバタ臭いところがどっかにあるはずだと。それが本当だと、一つの目安だと思いますね。だから僕は、名訳というのはあまり信用おかないです。ちょっと読みづらいけどその作家の味がわかったなというのがいいかなと思いますね。
それを考えずにすっと日本語に置き換えるような、ただ英語を日本語に置き換える作業を翻訳だとは思わない。できれば、そのまんま、文字通り直訳したいんですよ。でも、直訳しても意味が全然違いますから。英語はかなり広い意味を持っていますけど、日本語というのは、例えば形容詞なんかは、非常に密にできていますから。ぴたっと一点を押さえていますから、噛みようがないんですよね。それを噛み合わせるのが大変ですね。
それから、まだ翻訳を始めたばかりの頃に有名な作家の新訳をやらせてもらったことがあるんです。ミステリーだったんですけどね。何が書いてあるのか全然わからない。ミステリーだからわからなくていいのかな、なんて冗談を言っていたんだけどね。よく見たら、古典的な作家なんだけど、その作家のユーモアというのが、やさしい英語で書いてあんだけど、Heとかsheとかitとか、全部飛ばして訳しているから何がなんだかわからない。英語で読んでみて初めて意味がわかった。これはいい勉強をしたと思いました。
英語というのは、個人によって作家によって癖があるんです、文章にね。それが考え方の違いだから。そのクセをいかに取り入れて日本語として馴染ませるかというのが翻訳の難しさで、翻訳に創造性があるとしたら、そこなんです。その一点ですね。
ただし最近は、クライブ・カッスラーの場合でも、会話が面白いですからね。会話となると、登場人物の個性をいかに出すか、そっちに重点を置きますね。普通の会話のときでもアメリカ人独特の言い回しがありますからね、それを残そうと思うんです。それでああこれは面白いな、こういう言い方をするんだなという面白みがあったほうがいいと思うんですよね。
だから今訳しているクライブ・カッスラーの最新作では、実験しつつ訳しているんです。この人だとわかる限りはHeとかsheとかは極力省こうと思ってね。台詞だけで、これは誰の言葉だってわかるようにね。僕の場合はクライブ・カッスラーのダークピットとか登場人物を二十年も三十冊も訳してきているもんだから、わかっていますからね。それで、個性を植えつけて訳してきていますから。翻訳というのは本来は原作の臭みをいかに残すかということだと思いますね。それで日本語として読みやすいものだったら、名訳ですね。
〈日本人の読解力〉
編集部 翻訳家の仕事は以前とは変わってきているように思いますが。
中山 時代によって翻訳家の役割は大幅に変わってきていますね。むかしは、一言で言えば、翻訳書は教養を高めるために読まれていましたけど、今は英語が出来る人がいっぱいいる。ただし、これは問題発言になるかもしれないけど、日本語の質が落ちてきたというか、日本語の表現力はたしかに落ちていると思いますね。感情を表現する形容詞なんかは、若い人もいっぱい持っているけれども、読解力というものは落ちているんじゃないかな。
編集部 それは日本人全体のという意味ですか?
中山 そうですね。だから、翻訳書というのは、今は教養を高めるための物でも、外国を知るための手段でもないんですよね。今はテレビもあるし、旅行している人もいっぱいいるし。外国の品物だって、食べ物や着る物だって、たえず接触しているし使っているし。外国の知識を導入する窓口としての意味はほとんどなくなってきていると思いますね。だから、翻訳はいまに無用になるんじゃないかって思うんだよね。特定の文学作品とか、特定の哲学の本とか、植物とか科学とか、そういう本はあるだろうけど、ごく一般の小説の意味というのは、相対的に落ちていくのかなと思いますね。
これは翻訳書だけじゃなくて。昔は、小説が人生のものの考え方に影響を与えることがずいぶんあったと思うんです。こういう風に生きたらいいのかな、というのを小説を参考にしたという経験がね。今は、それがだんだん薄くなってきているんじゃないかな。そういう意味では、翻訳書だけでなくて文学全体の影が薄くなってきているような気がしますね。もっともっと本を読んでもらいたいと思いますね。本を読む時間はきわめて減っているのではないですかね。このあいだ、たまたまテレビで見たんだけども、日本では一日に八時間だか十時間、テレビを観たりスマホをやっているっていうじゃないですか。
それで、大学入試でも人物主義で入れるっていう話があるでしょう。冗談じゃない。それでなくても、学力が落ちてしょうがないのに。高校時代に、「ヘミングウェイを暗記しないと卒業させない」ていうくらいの先生がでてくれればいいと思うんですけどね。
編集部 大学入試で人格をみるということは、高校生までに人格形成をしておかないといけないということになりますね。
中山 誰が人格形成をするんですかね。このあいだ、友達三人で集まって、俺たちが悪かったのかな、なんて話になってね。我々の子どもたちや孫の世代のことですからね。学校の先生ではなくて、そういうことは親がやることではないかと思うんですよ。
テレビもすごくいい役割があるんだけど、読解力とか、読書をすることによって想像力を育てるということが、残念ながら落ちてきている。良い本とか、良い小説がもっともっと紹介されるようになるといいんですけどね。
〈誤訳に思うこと〉
中山 インターネットの機械翻訳なんかを見ると、いかに翻訳が難しいかということがわかりますよね。定訳を調べようと思って、インターネットで見て訳が出る場合があるでしょ。その説明が、何がなんだかわからない。さっき言ったようにね、英語にはいろいろな意味があるでしょ、それを機械的にぱっと日本語に当てはめるだけだからまったく文章になっていない。
三十年位前かな、機械翻訳ができて、翻訳者なんか全然いらなくなるって言われたけど、そんなことは無理ですね。人間の頭のほうがパソコンなんかよりはるかに良い。翻訳者が機械に取って代わるなんて日はまだ百年くらいは来ないと思います。そういう意味では翻訳者は貴重だとは思いますけどね。結局、翻訳の難しさは作品に惚れて、作中人物に共感するかどうかということが必要ですよね。この人はこういう風に感じているんだなということがわかってこないと、訳語を選べないんです。良い意味の黒子になる。それと、誤訳できたら大したものですよ。
編集部 誤訳ができたらというのはどういう意味ですか?
中山 誤訳というのはレベルの問題ですけどね。この作家はここまで言いたいんだろうなと踏み込めるようになれば、そこで初めて間違いが起こりうるということです。当たらず触らずの訳では、書評家でも普通の読者でも、ああそんなもんかって読んでいるだけでしょ。そこをもっと踏み込んでみると、なんだこれ、そんな意味があるのかということになってくる。
昔、吉田茂の息子で吉田健一さんという、イギリスのケンブリッジで育った人が、誤訳を指摘されたんです。すると「冗談じゃない、指摘したほうが間違っている」って言ってましたよ。吉田健一さんはケンブリッジで何十年も暮らして、シェークスピアも訳している人なんです。上智大学の有名な先生が誤訳の本を出してずいぶん売れたんです。吉田さんは、「あんなことを言う本人が誤訳だらけなんだから、私はまったく気にしませんよ」って言ってましたね。
編集部 福田恆存さんの『老人と海』(新潮文庫)のあとがきには「今まで誤訳を指摘してくださった方々に深謝します」って書いてありますね。
中山 あれは有名な話だけど、イルカの訳で失敗しているでしょ。あれは、シイラのことなんだけど、ずいぶん叩かれたらしいんですよ。 “dolphin”って確かにイルカなんだけど、2番目の意味にシイラがあるんです。ちょっとした間違いですけどね、叩かれたらしい。これはさっき言った東大の水産学部の教授だった末広さんが教えたらしいんですけどね。僕も末広さんから聞いたことがあるんです。それは間違ってもしょうがないかもしれないけど、僕に言わせれば、ここだけの話、あれは編集者が悪いね。海の中だからイルカがいないことはないけど、この場面では出てこないんじゃないかと思わないとね。戦後間もない頃でしたから、ばたばたと出しちゃったんでしょうけどね。誰かが直してあげないとまずいと思いますね。まあ、ヘミングウェイの良さをわかってくれればそれでいいと。本質さえ掴んでいればいいという考え方もあるでしょうけどね。
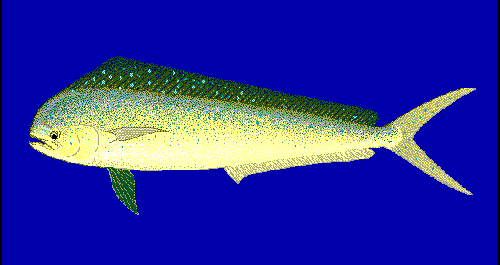
(シイラ)
〈いい本を読みたまえ〉
編集部 最後に若い人へのメッセージをお願いします。
中山 第一に、人生というのは自分では一回しか経験できないわけです。それは限られた経験ですよね、たった一回ですから。だから、世の中を幅広く知るためには、他の人の人生をたくさん知る必要があるわけです。そのためには、本をたくさん読みなさい。良い本をね。良い映画とかね。芝居でもいいですよ。自分の人生を豊かにしてくれるのは、他の人の生き方を見ることですよ。それを集約して見せてくれるのが、本とか映画だからね。良い本、良い小説、良い映画を若いうちにいっぱい読んだり観たりすることをお勧めしますね。やっぱり、有名な定評のある本は読んでもらいたいですね。それだけですね。それは是非してもらいたい。それ以外には、あまりえらそうなことは言えないけど。
編集部 そういう意味でも、このヘミングウェイの『老人と海』はお勧めですね。
中山 ええ、ヘミングウェイでもなんでも読んでください。いろんな人と出会える機会というのは限られているわけです、人生において。小説でも映画でも、そういった主人公の生き方、暮らし方、人生を読むと、間接的にそうした人の人生を経験できて、読んだ人の感受性が豊かになる。そうすれば、人に対する思いやりとかも自然に出てくるかもしれない。翻訳本に関して言えば、シェークスピアでも何でも、読んでみると勉強になるだろうから、若い、感受性のあるうちに良い本、良い映画を観ることをお勧めします。じじいからの提言。(笑)。
編集部 ありがとうございました。大変勉強になりました。